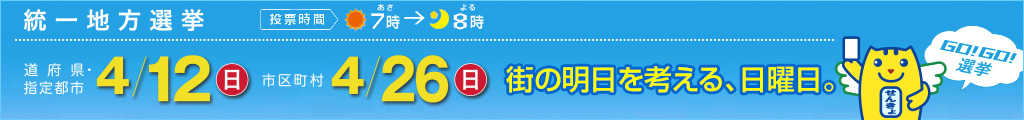統一選意識調査データ
明るい選挙推進協会が前回(第17回)統一選後に実施した、有権者の意識調査結果から一部を紹介します。
調査対象者は全国満20歳以上の男女3,000人で、無作為抽出、面接調査により実施し、1,910人の方に回答いただいたものです(回収率63.7%)。
選挙関心度
今回の統一選(知事選、道府県議選、市区町村長選、市区町村議選)について、あなたはどれくらい関心を持ちましたか
「非常に関心を持った」という回答が最も多いのは、市区町村長選挙の26.3%(前回33.9%)、次いで知事選挙の21.8%(前回27.9%)、市区町村議選挙の21.6%(前回29.0%)である。道府県議選に関しては、「非常に関心を持った」が14.9%(前回21.0%)で、他の選挙に比べて低く、逆に「ほとんど関心を持たなかった」「全く関心を持たなかった」という回答が他の選挙に比べて多い。前回に比べると、全般的に選挙への関心度は低下している。

関心のある選挙
(国政選挙も含めて)ここに6 つの選挙があげてありますが、あなたがとくに関心をお持ちになる選挙を2 つあげてください
最も関心が高いのは衆議院議員選挙で、過半数の人(56.9%)が関心を持っている。同じ国政選挙でも、参議院議員選挙に言及した人は2 割を超えた程度(23.5%)に過ぎない。地方選挙に関しては、都道府県に比べ市区町村の選挙の関心が高く、また、議員選に比べ首長選の関心が高いという傾向が読み取れる。なお、どの選挙にも関心を示さない、あるいはこの質問に「わからない」と回答した人が9.2%もいる。
| 関心のある選挙 | 「ある」(%) |
| 衆議院議員総選挙 | 56.9 |
| 参議院議員通常選挙 | 23.5 |
| 都道府県知事選挙 | 28.4 |
| 都道府県議会議員選挙 | 11.4 |
| 市区町村長選挙 | 30.7 |
| 市区町村議会議員選挙 | 22.5 |
| どれも関心を持たない | 8.2 |
| わからない | 1.0 |
候補者情報の不足
地方選挙で『候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る』という声があります。最近の地方選挙で、あなたは、そうお感じになったことがありますか
候補者情報の不足を認識している有権者の数は、増加傾向にある。第10 回統一選(昭58)から第12 回統一選(平3)までは、その割合が30%台の前半であったのが、第13 回統一選(平7)から40%を超え、今回の統一選では50.1%と半数を超えた。その50.1%の回答者に、そう感じたのは「どの選挙でしたか」と尋ねたところ(複数回答可)、道府県議選が最も多くて65.1%、次いで市区町村議選48.1%、知事選36.2%、市区町村長選32.2%であった。
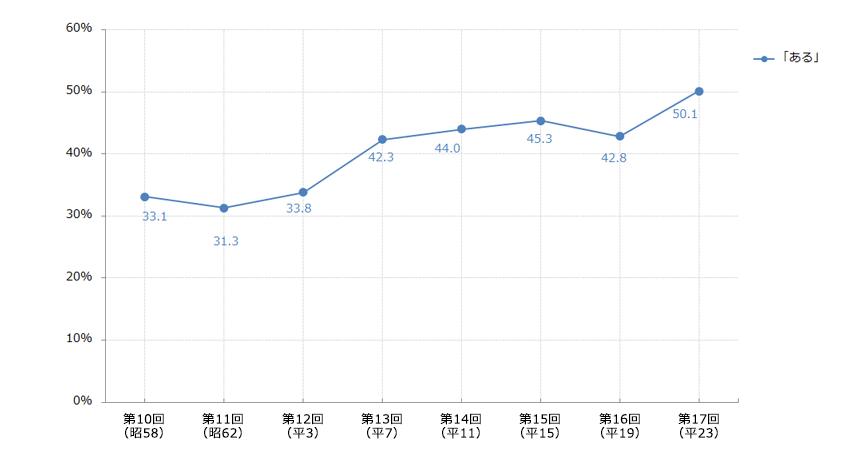
政治の評価
日本の政治、都道府県の政治、市区町村の政治をそれぞれ全体として考えた場合、「非常によい」「まあよい」「あまりよくない」「非常に悪い」「どちらともいえない」のうち、どういう感じをお持ちになりますか
それぞれの政治に対する「非常によい」「まあよい」の肯定的評価を合計してみると、一貫して「日本の政治」より「都道府県の政治」の方が、また「都道府県の政治」より「市区町村の政治」の方がより評価が高い。今回、「都道府県の政冶」および「市区町村の政冶」に対する評価は前回に引き続き上がったが、「日本の政治」に対する評価は大きく下落して1 割を切り、過去最低となった。
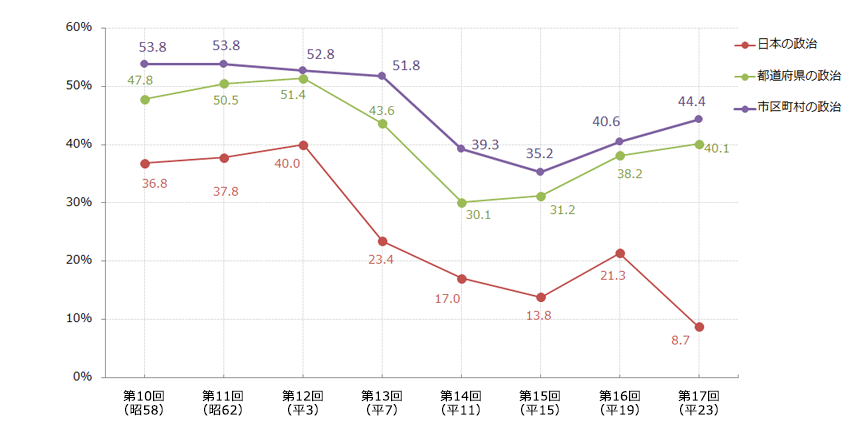
議員の役割
県(都道府)議会議員(市(区町村)議会議員)に対してどのような役割を望まれていますか
今回の調査で初めて尋ねた。都道府県議会議員、市区町村議会議員ともに、「地域の発展を考える」が最も多く、次いで「県・市全体の将来を考える」「地元の面倒をこまめにみる」の順になっている。「地域の発展を考える」という役割は市議会議員よりも県議会議員により多く期待されており、逆に「地域の面倒をこまめにみる」という役割は県議会議員よりも市議会議員により多く期待されている。
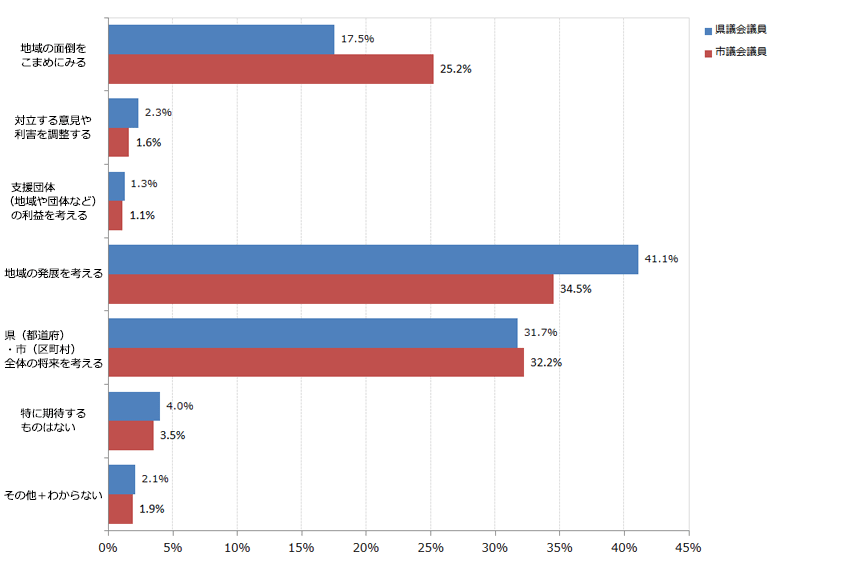
考慮した問題
知事選挙、県(道府)議会議員選挙で、あなたはどのような問題を考慮しましたか
知事選、道府県議選ともに、最も選択率が高かった項目は「医療・介護」、次に高いのが「景気・雇用」で「高齢化」「年金」がこれに続いている。「医療・介護」は前回同様第1 位ではあったが、選択率は前回より減少している。これに対し「景気・雇用」は選択率が大きく増加し、第2 位(前回は知事選で同率2 位、道府議選で5 位)となった。また、「災害対策」の選択率も大きく増加したが、全体の順位はさほど高くなかった(知事選で7 位、道府議選で8 位)。
| 知事選 | 道府県議選 | |||
| 16回(平19)(%) | 17回(平23)(%) | 16回(平19)(%) | 17回(平23)(%) | |
| 医療・介護 | 46.8 | 39.4 | 46.6 | 41.0 |
| 景気・雇用 | 29.0 | 38.7 | 25.0 | 38.1 |
| 高齢化 | 28.8 | 34.9 | 29.6 | 30.5 |
| 年金 | 27.3 | 32.6 | 29.9 | 30.6 |
| 税金 | 29.0 | 31.0 | 26.4 | 27.2 |
| 教育 | 25.6 | 22.3 | 24.1 | 17.4 |
| 災害対策 | 11.1 | 17.8 | 9.0 | 13.8 |
| 環境 | 20.0 | 17.3 | 16.0 | 11.4 |
| 国政の動向 | 6.9 | 13.0 | 6.3 | 10.9 |
| 少子化 | 15.5 | 11.8 | 14.6 | 11.4 |
| 地域振興 | 10.1 | 10.9 | 15.3 | 16.2 |
無投票当選の是非
今回の統一選では、道府県議会議員選挙や市区町村長選挙などに無投票当選がありますが、これについてあなたはどう思われますか
地方選挙においては、無投票当選者が多く、第17 回統一選でも、市長15 人、指定都市市長1 人、町村長58人、道府県議410 人、市議116 人、町村議893 人の合計1,493 人が無投票で当選した。もともと「無投票になっても止むを得ない」と考える人の方が「投票なしで決めるのはおかしい」と考える人よりも多かったが、第12回統一選(平3)頃から「投票なしで決めるのはおかしい」と考える人が徐々に増加し、前々回(平15 年)は逆転した。しかし、前回(平19)および今回(平23)は、「無投票になっても止むを得ない」と考える人の方が「投票なしで決めるのはおかしい」と考える人より再び多くなっている。

調査結果をとりまとめた報告書は明るい選挙推進協会のホームページでご覧いただけます。こちらからご覧ください。